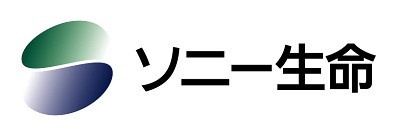余命の力

山田啓蔵さん(61)
芦屋実行委員長
フィリピンのミンドロ島。部族マギアンは裸でばん刀をふるい、ジャングルを駆け回る。どんな暮らしをしているのだろう。青年山田啓蔵は胸躍らせて、焼畑農業にいそしむ彼らのそばに学生仲間6人と陣を決めた。実は40年先に闘病、そしてリレー・フォー・ライフに出会ったときに感じた気持ちの原点は、ここにあった。
理学部の大学生になってすぐ、探検部に入った。息つく暇もなしに学術探検を計画、仲間や教授を口説きまわる。地図を前に綿密な調査プランを一人でつくり、大阪万国博覧会の年に島へ渡った。気配りの男は大きな缶50個を船便に乗せ、キャップと医療班を兼ねた。毒グモ、毒ヘビもいるはずだ。「できるだけのことはしよう、しかし何かあったらあきらめときー」と説得し、人間が傲慢にならないよう自然の力に従うことを信念にした。
「名医がいる」という言葉が広がり、左腕が膿で丸太のように腫れあがった部族の男が困惑の表情で助け船を求めてきた。昆虫採集のメスを消毒して切開し、それを何日か繰り返したとき、男は晴れ晴れとした表情で何日もかかる住まいへの帰途につく。3カ月の滞在は、「何でもやればできるんだ」という前向きな気持ちに変えさせた。

残業100時間、多い月はその倍という激務も若かったからこそ楽しい思い出だ。入社した1972年以降は、歯磨き業界も大忙しで、システム、営業本部、企画、社長室、市場調査などいくつもの部長、役員として最前線にいた。
「これ、まずいなとすぐわかりました。たぶん、あかんやろう」。がん細胞が肺の主要部を取り巻いていた。どうもスイングがうまくできないとゴルフ場で気づき、てっきり50肩だと思った。会社の健診で、思わぬX線写真を見せられ、家族にどう話すか、自分が居なくなっても暮らせるのかとまず思ったという。
血小板が10万ないと抗がん剤治療が始められないのに、足りない。放射線と抗がん剤を組み合わせて効果があると言われたのに、片輪飛行になる。もとより、リンパ転移があり、手術はできない。「これでお別れかという気持ちで、知り合いにたくさん会っていました。人恋しくてね」。周りの患者の話を聞きたくても関西にはその場がない。
肺がんⅢB。医師はうなずかないが、自分で察するに余命は1年かせいぜい1年半とみた。3カ月単位で人生を考えることにした。いろいろな人に会ってみたいなと思いながら。
リレー・フォー・ライフ2009in芦屋の人の渦の中に、笑顔の男がいた。いつも笑顔だった。「リレーには色々な人がいる。厳しい状況でも頑張っている。勇気づけられる。ここですね、患者にとって仲間ほど大切な宝はない」。2010開催にあたり、山田は実行委員長を若い妻をがんで亡くした大隅憲治から受け継いだ。やはり最愛の妻を亡くした城村勉、サポートに熱い気持ちを持つ中澤清浩が支えることにした。4人衆の誕生で、芦屋は新たな旅立ちをした。
「ひょっとして今しか役立てないかもしれないと思った。1年は動けるかと。おまけの命だからできることをやろう」。若いときから探検や新規事業で挑戦し続けた男が、決断と生きる姿勢を示したときだった。「リレーでは、みんなの意見を聞き、地域に密着したあり方をどう進めることができるか探りたい。リレーはつぶさない」。これこそが、病気と向き合うつらい思いに、探検魂で折り合いをつけた山田流生き方ということだろうか。
(敬称略)