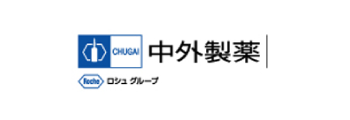書評より(2025年2月6日)
「えっ、これは何?」一月下旬の日曜日、中国新聞の書評欄を見て驚いた。おそらく十月だったと思うが、この本の書評を読み、本を買って読んだ体験がある。同じ本の書評を二度出すことはないだろうから、もしかしたら読売新聞かもしれない。
その本とは松本俊彦氏と横道誠氏の往復書簡を書籍化した「酒をやめられない文学研究者とたばこをやめられない精神科医が本気で語り明かした依存症の話」という長い題名の書籍。松本氏は私が尊敬する精神科医であり、著書は五~六冊購入して読んでいる。それにこれだけ長い題の書籍なので忘れたり、間違えたりもないだろう。よし、もう一度読んで、エッセイにしようと思った。
まずは「依存」と「依存症」について。依存とは「それがあるからがんばれる」「それがないとがんばれない」といったものがある限り、依存しているといえる。悪いことではない。問題は依存症の方。たくさんのデメリットが明らかなのに、それでもつかの間の安堵を求めてやまない「不健康な依存」それが依存症という病気。
「依存症の本質は快感ではなく苦痛であり、人に薬物摂取を学習させる報酬は快感ではなく、苦痛の緩和である」と指摘し「自己治療仮説」という考え方を提示した依存症専門医がいる。
「自己治療仮説」といえば、私が今の職場に就職してしばらくしたころ、広島市で行われた信田さよ子氏の講演会で聞いた。そこで「福祉職としては依存症の利用者にどのように接したらよいのでしょうか」と質問したところ、「いい質問ですね」と言われたが、その後の答えを憶えていない。
さて、「ハームリダクション」とは何か。世の中には薬物使用を続ける当事者が必ず一定数いることを前提とし、薬物使用を減らすのではなく、薬物使用による二次的な弊害を提言することを目指すという考え方。
具体例としては断酒困難なアルコール依存症のホームレスに、栄養たっぷりな炊き出しとともに、少量のアルコール飲料をふるまうという支援。この試みは死亡率を劇的に低下させた。「何が何でも飲酒はだめ」というスタンスの支援では、支援者が当事者とアルコールについて率直に話し合うという場が失われ、当事者の孤立を引き起こす。
ところで市販薬のオーバードーズが問題となっているが、快楽を得たくて飲んでいる人ばかりではない。苦痛を一時的に緩和したり、困難を解消したり、中には「消えたい」「死にたい」という気持ちを紛らわすために過量服薬している人もいる。「今すぐ死ぬ」というのをほんの少しだけ延期するという意味において、短期的には自殺に対して保護的因子となっている。
また、依存症者家族の支援は本人の支援と同じくらい重要。「共依存」という言葉はほとんどネガティブな意味で使われている。だけど、共依存やイネイブリングは、支援につながった依存症者とその家族の特徴であって、家族があっさりと本人に見切りをつけたケースの特徴は反映されていない可能性あり。一時的にはそれらはボジティブな機能を果たしているのでは。
Ask発行の季刊誌「Be!」には「減酒より禁酒を」といった専門医や家族の声がよく載っている。また二月十五日、オンラインで「ダメ!と止める支援からハームリダクション的な支援へ」という講座が松本俊彦氏を講師に開催される。しっかり学習したい。